1齢幼虫
ネットでは卵の孵化まで1週間が目安とのことなのに2週間たっても孵化しない、もうダメかと油断し始めた頃。

うおおおおー孵化してるー結局この子達は17日もかかった。
小さいだいたい5mm、桜の葉を摘んで一緒にケースに入れた保護できた個体は11匹。確認できた卵の抜け殻は24個だった。
13匹も保護できなかった。小さな死骸も3つ見つけた残念!

小さな褐色の芋虫、餌替え時に全数確認とるのが大変でした。
2齢幼虫



脱皮をして、体色が緑になり体長は1.5cmぐらいです、この辺りから少しづつ大きさに個体差が出始めます。↑可愛い休憩のポーズ
3齢幼虫


さらに脱皮をして体長が3cmぐらいになります。背中のトゲ?が花火みたいで綺麗でしょ、相変わらず休憩のポーズは同じ。
4齢幼虫



3回目の脱皮をして体長はだいたい5-6cmに。脱皮した後、頭がおおきくなって、葉を食べた分だけ体が順に大きくなっていきます。
終齢幼虫


4回脱皮を終え終齢幼虫になります。大きい個体は12cm、小さくても8cmここまでくると観察がとても楽しくなってきます。
ウンチの観察


一房の形はハート形、匂いは桜餅の良い香り、そして1段6房で5段構成計30房で1個ができてて、1匹1日大体68個排出します。
足の観察
前3対は主に食べ物を食べる時に葉っぱを支えるために使います。
後ろ5対は移動や食事の時に体全体を支えるために使います。
前3対の先っぽには静止画で見ていただければ分かるように鍵フックのような小さな爪がついています。 →
これで葉っぱ引っ掛け固定。
動画の後半で幼虫の体が著しく汚れているのですが、これは他の個体が蛹化するときに排出する液体がついた為で、けして怪我をしているわけではありません。

後ろの5対ですがとても複雑です。
左右の1対で挟むわけですが、足裏の粘着力と小さな沢山のトゲが見事に連携します。
言葉で表現すると
ピッタ、グッサ!となります。柔らかい肉厚な足裏でキャッチさらに左右で挟む瞬間肉から小さなトゲがニュウと出てきてグサッと刺さります。この足で指を這われると無理やり剝がせません。
小さな棘が皮膚に刺さっている状態です。無理には剥がせませんが、動く時には何の問題ありません。

食事の観察
前3対で上手に挟んで小さなフックで引っ掛け引き寄せシャクシャクリズム良く食べていきます。ほんとに音も聞こえてきそうです。
食べるのは葉だけではなく、葉と枝の間の柄の部分もよく食べます。なので大食いですが食い散らかすではなく食い切る感じです。
口の観察
は・ハ、歯が見えた‼しかも、お歯黒。正確にはアゴなんですが、絶対歯に見える!
終齢幼虫は大きいので,いろんなところがよく見えます。
休息のポーズは、1齢の時から変わりませんが、大きくなった分、前足も、頭も,目も、唇?も、目は顔の両脇の黒い辺りに片側5つずつレンズのような部分が何となく確認できます。成虫のような複眼ではありません。
口の部分はかなり複雑、唇っぽい部分も歯も葉っぱを端から食べやすいように、縦型に配置されてます。食前食後には、舌みたいな器官で、掃除を怠りません。触覚も絶え間なく良く動いています。
脱皮の観察



脱皮をするとまず顔が大きく白くなります。その後顔は濃くなり、体は食べた分だけ大きくなります。
画像は4齢から終齢幼虫に脱皮した後の抜け殻です。食べられる前に撮影しました。脱いだ皮もちゃ��んと食べます。
4齢幼虫(画像左)と3齢幼虫(画像右側)ではこんなに大きさに違いがあります。脱皮1回で、こんなに大きさが変わります。
透けた体の観察
命の脈動
よく動き回るのであまり気づかないのですが、体は半透明で。ジッとしてくれさえすれば、内臓の脈打つのが透けて見えます。昆虫なので心臓はありませんが、その代わり、背脈管という器官が有り心臓と同じように体液を体全体に行き渡らせます。されに葉っぱを消化するための器官もあるので、それらの動きが分かるように撮影しました。
ドックン!ドックン!と鼓動も聞こえてきそうでしょ。
蛹化の観察

幼虫の�間フンはするのですが、排尿は全くしません。ただ蛹になる前には余分な水分を一気に排出します。
綺麗な半透明の緑色だった体が蛹化前にくすんだ茶色になります。
気に入った葉っぱが見つかれば、糸を出して繭を作り始めます。
葉っぱが上手く紡げればその内側では繭の制作が進行しています。
飼育時基本情報
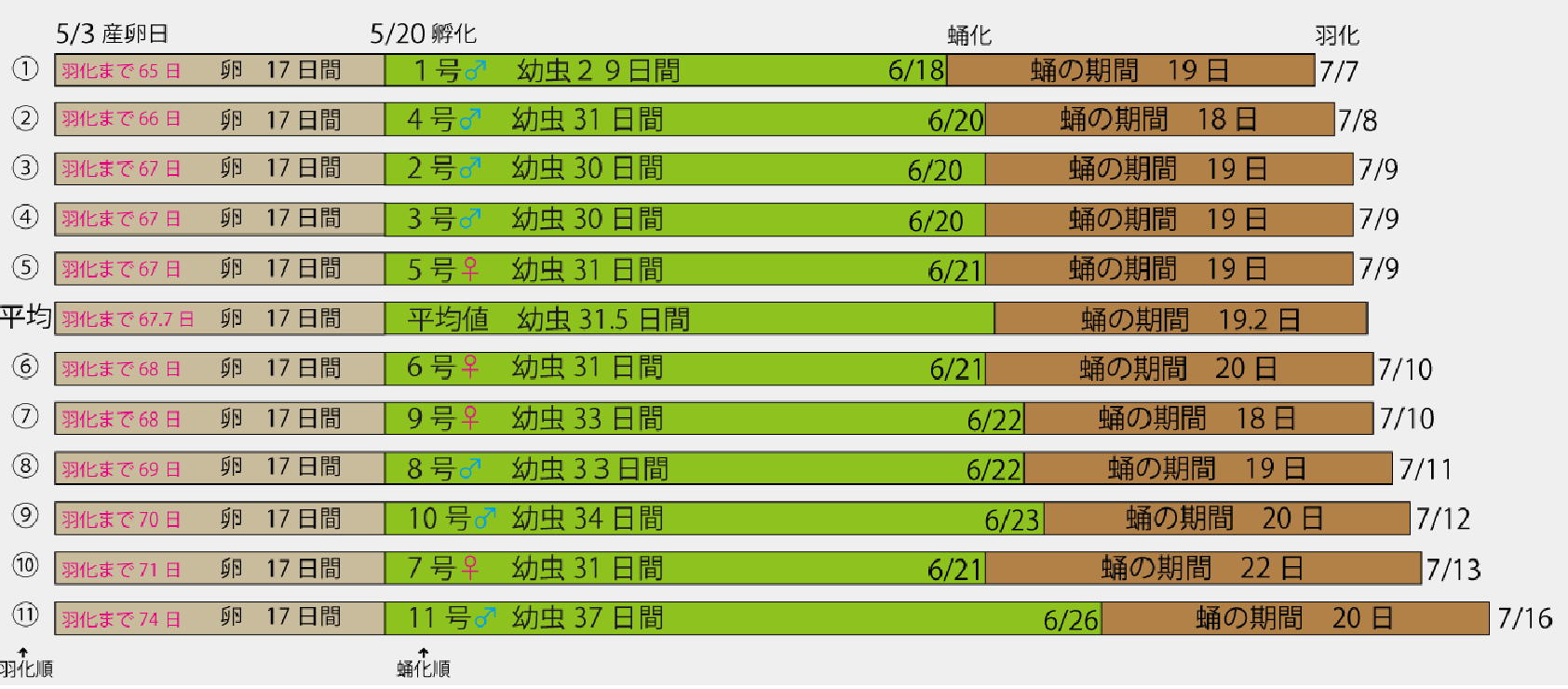
食性…ウメ、リンゴ、サクラ(バラ科)、クリ(ブナ科)、ミズキ(ミズキ科)、ザクロ(ミソハギ科)やカエデ(カエデ科)カバノキ(カバノキ科)、と多食性
今回はサクラで、飼育しました(ウメとサクラを一緒に与えてみましたがサクラへの食いつきがすごかったので)多食性ですが飼育中に葉の種類を変えることは良くありません。(最悪、一生懸命育てた幼虫が死んでしまいます。)
さあココまでくれば後は羽化を待つだけです。




